"AI"や"ロボット"技術の発達で人の仕事が奪われる?
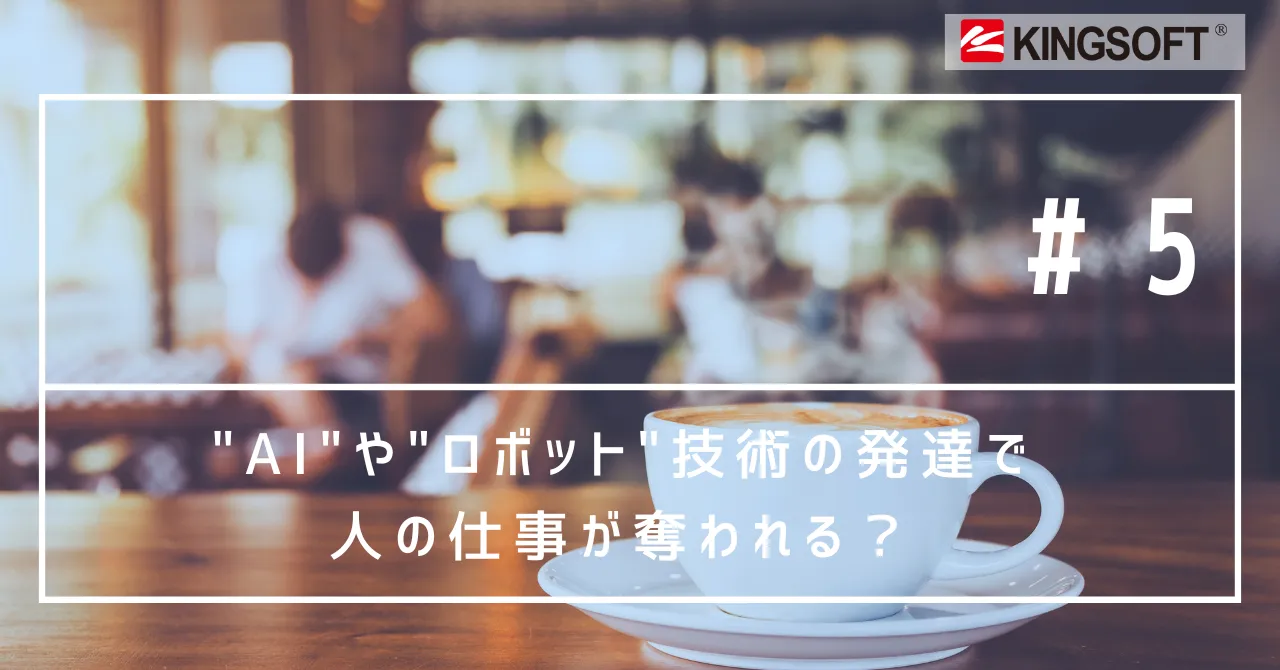
AIやロボット関連の話になると、度々話題に上がるのが『AIやロボットによって人の仕事が取って代わられる』というテーマです。
もし本当にAIやロボットが人の代わりに業務を行い、多くの人の仕事がなくなってしまうのであれば、それは大変なことです。しかし実際のところ、本当にそうなのでしょうか。
今回はロボットを取り扱っている私たちの目線から、このテーマについて考察してみたいと思います。
AIやロボットにはできないことがたくさんある
"AI"や"ロボット"と聞くと、なんでもできる全能なイメージを持っている人もいるのではないでしょうか。確かに映画やアニメの中に登場する"AI"や"ロボット"は、あらゆる知識を持っており、ポケットから超便利なアイテムが登場したり、空を飛びレーザービームを出し人類を救ったり、と、まさに何でもできてしまう人知を超えた存在です。
ですが実際のところ、現段階では"AI"や"ロボット"のできることには限りがあります。まずは最近よく目にするようになってきた、案内ロボットや配膳ロボットを例に挙げて考えてみましょう。
案内ロボットは、文字通り設置先の施設を案内するインフォメーション的な役割を担うロボットです。企業の受付や、駅・空港などの公共交通機関、ショッピングセンターなどの商業施設の案内係として活用されています。案内係としての役割から自律走行やコミュニケーションといった機能が搭載されていることが多く見られます。
確かに案内ロボットは人と会話をすることができ、目的地への誘導案内も可能なため、人に代わってオフィスで受付業務を行ったり、商業施設や公共交通機関でインフォメーションスタッフの業務を一部代替することは可能です。また、店舗情報やセール情報のご案内、時刻表や乗換案内など、質問の多い事項や一般的な受け答えは難なくこなせます。
一方でロボットのみでは対応できないことがあるのも事実です。例えば、拾得物対応や迷子対応などその時々によって対応が異なる業務の代替はまだまだ難しいのが実情です。こうした事案が発生した際にロボットにできることは、イレギュラーごとの問い合わせ窓口を案内することのみ。そしてその先の対応は人がおこなう必要があるのです。
もう1例として、飲食店などでホール業務を担う配膳ロボットでも考えてみましょう。配膳ロボットは、文字通りお客様にお食事などを配膳するロボットです。機体の棚の部分にお食事などの運搬したい物を配置することで、任意のポイントへとモノを届けることができます。
弊社が取り扱う『Lanky Porter』の場合、頭部のディスプレイからタッチパネルで操作が可能。メインである配膳の機能に加えて、新規でご来店されたお客様の座席へのご案内や、食べ終わったお皿をお下げする下げ膳などの業務を任せることが可能です。
但し、こちらの配膳ロボットもホール業務のすべてを担えるかと言われると、そうではありません。オーダリング業務や会計業務などは配膳ロボットの機能として搭載されていないため、これらの業務には人の手が必要です。
つまり案内や配膳、下げ膳といった業務は配膳ロボットが中心となっておこないい、人はオーダーの取得やお会計に専念する、といった切り分けが必要になります。業務を一部代替することができるため、何人かの人員を減らすことはできますが、全ての業務を担うことができるわけではないため、完全に人が必要なくなるかと言われると、そういうわけではないのです。
全てをロボットに任せると逆にコストがかかる
既存のシステムと連携したり、追加開発を行うことで、難しいとされている業務の一部はロボットでも代替できるようになります。
例えば、前項でも挙げた配膳ロボットの場合、オーダーシステムや決済システムと連携することで、配膳や案内、下げ膳のみならず、オーダーやお会計といった、一通りのホール業務をこなすことができるようになります。
ですが、このように他のシステムと連携させてみたり、追加の機能開発をするなど、複雑にシステムを構築することで、ロボットの導入費用は格段に高価なものとなります。導入費用が高くなると、結局のところ人が業務に従事したほうがコストが安い、という本末転倒なことが起きます。
当然いくら費用をかけても、ロボットにはできないことがまだまだあり、こうしたコスト的な観点からもまだ人の仕事をロボットが奪う、なんてことは考えづらいのが現状なのです。
そもそも今後の日本社会では労働力が不足すると考えられている
そして、そもそもの日本社会は"超"が付くほどの高齢化社会。高齢者の人口は増加し、労働力である生産人口は年々減少しています。こうした課題を解決するために国を挙げて女性や高齢者の労働力を有効利用する方策が取られるほど。このような日本の社会情勢の中で『"AI"や"ロボット"が"人"から仕事を奪い、人の仕事がなくなってしまう』なんてことはまず考えられません。むしろ"AI"や"ロボット"の力は、不足している生産人口が持つ労働力を補完する役割を担うのではないでしょうか。
我々が住む日本の状況を鑑みても、人が得意なことは人が行い、"AI"や"ロボット"の方が得意なことは"AI"や"ロボット"に任せる。これからの時代はこうした切り分けを行うことで、今後訪れるとされる"人材不足"や"人件費の高騰"に対応していく必要があると考えられます。
まだまだ人の仕事はなくならない
更なる技術進歩によって、より優秀なAIやロボットがより安価な価格で、そして大量生産できる未来が訪れるのであれば、その時は人の仕事がAIやロボットに取って代わられるのかもしれません。
ですが、現状の技術や今のロボットの浸透率、そして現在の日本社会の状況などを踏まえると、近い未来にAIやロボットが人の仕事を奪うことはないでしょう。それよりも今後必ず訪れる、労働力不足という課題に向けて、AIやロボットを活用したオペレーションの検討が必要なのではないでしょうか。